
小型アンプ聴き比べ大会

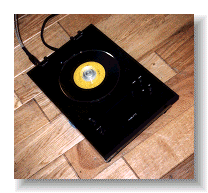
|
3月11日の例会では「小型アンプでも聴いてみるか」という企画となりました。とはいえ、それほど気合の入ったサークルでもないので、別に小型でなかろうが、自作してなかろうがアンプを持ってこれる人はもってくる、ということですね。DACやらCDPでも構わないわけです。 当日のCDPを何にするかということで、まず芦澤師匠のマランツCD-46改と鈴木君(このあと登場の「鈴木さん」とは別人)がもってきた47研究所のCDP 4713を比較しました。さすがに1万円未満 + 改造材料費・手間賃 対 28万円 の戦いは、28万円すなわち4713の勝利となりました。違いはやはり細かいニュアンスやら音の清冽さというようなところでしょうか。でもマランツCD-46改のコストパフォーマンスを考えると、1万円当たり単価で勝負したらCD-46の勝ちでしょうね。
|
|
まあ、気に入る音さえ出ていれば、勝とうが負けようがどうでもいいことなんですけど。写真は4713です。鈴木君の自作ノン・オーバーサンプリングDACと組み合わせて使います。 4713に載っているCDは、自主制作にちかいような状態で作成されたものらしいです。とても素直に録音された女性ボーカルものなんですけど、「一人に一つずつ持っているものぉー、それは命と孤独ーっ...」と歌う、なんか淋しい歌詞です。一緒に飲み屋にはいきたくないタイプですね。たしかに。 確か一番手は、鈴木さん(?)持参の普通のシングルアンプ。球の型番は不明。素直で真空管らしい音がしてました。ボリュームが4つついているのが謎です。音量と、あとなんなんでしょう。NFBの量かなぁ? |
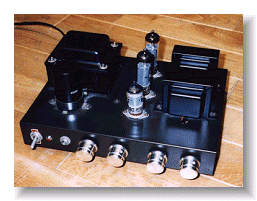
|
 TEACの業務用ブランドTASCAMのPA用アンプ PA-20Mk2のノーマル品。オーディオ屋さんには置いてなくて、楽器屋さんにおいてあります。1万円ちょっとくらいの値段です。マルミさん時代からFaradayでは、改造用ベースとして愛用されている機種です。
|
|
1. 使用抵抗器を変更。 2. 整流ダイオードを、ショットキーバリアダイオードに変更。しかも半波整流! 3. 電源のコンデンサを3300μF2個から、1000μF2個に変更。 4. ボリューム部分は、基板を使用して配線されていた物を、ダイレクト接続に変更 5. 入出力ターミナルを変更 6. 電源ケーブルがへたっていたので、新品に変更 他にもあったけど、とりあえずこんなところかな。 |

|
|
音なんですけど、やっぱりノーマルTASCAMよりもクリアーかつ柔らかく、BOSEの方が優れていると思います。この日は他にいろいろなアンプが登場しましたが、私はこれが一番よかったんではないかと思いました。まあ、みなさんいろいろと意見があるかと思いますが。 あと、なぜか写真を撮り忘れていたみたいなんですけど、BOSEとよく似た位置づけにあるJBLのなんとかかんとか、という小型アンプが出品されました。これもICはSANYO製だったような。平たい円筒形で、周りが放熱器になっているやつです。みんなは「カブトガニ」と呼んでました。藤川さんがこれのノーマル品と、ぐっちゃーさんが改造した品を持ってきてくれました。 で、これが低域をブーストしてあるのか、やたら低音がでます。高域もあきらかにキャンキャンしてます。どうもパソコン・スピーカーのアンプとして設計されているみたいです。ぐっちゃーさんが弄ったものは、高域のキャンキャンさ加減が緩和されているのですが、全体の傾向として「濃いー」音であることには違いない。あ、JBLだからこれでいいのか。
|
 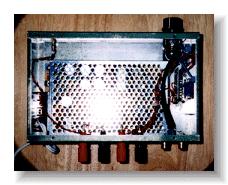
|
さて、ここでICがSANYO製からフィリップス社製にかわります。いま、田中さんあたりが注目しているIC TDA1552Qです。田中さんのコメントをそのまま転載。
上記アンプは全てBTLステレオICの TDA1552Q 使用。このICは、最低必要な外付け部品はコンデンサ2個のみ(左右チャンネルの入力コンデンサ)だけで、あとは、VR、ピンジャック、SP端子、それと、プラス12-18V電源とアースをつなぐだけで完成。
その理由は、下の写真。中身を空けてびっくり電源はスイッチング電源です。オーディオ用としては評判のよくないスイッチング電源を使っていたわけです。
|
|
田中さんいわく、部品はぜんぶそこらへんにあったものらしいです。制作費は全部あわせても5000円いってないらしいです。だいたい、部品ってもケースとジャンクの電源と、コンデンサ2つ、ボリューム一個、あと端子類ですから。うーん、これでこの程度鳴るなら、細かいこといわなければこれでいいんではないでしょうか。って、こんなこと言い出したら別にオーディオなんかにこだわる必要はないよねぇ。
|
|
となりの写真がCDPを出品した鈴木君の作品。「緑のたぬき」と同じICを使ったものです。こちらは、電源部が別になってまして、電源も普通の非安定化電源です。本体のサイズはだいたい昔のポケットベル程度の大きさです。筐体はアルミダイキャスト製。 音の傾向は、こっちが「緑のたぬき」よりも滑らかです。ただ低域の馬力はやはり弱い感じ。とはいえ鮮度よい感じでなかなか好印象です。このTDA1552Qをスピーカーユニット1つにつき1個ずつ使ったマルチアンプ・システムなんか面白いでしょうね。スピーカーユニットの端子にIC直付けしたらどうなるんでしょ。ユニットからの振動の悪影響が強いのか、それとも必要悪であるスピーカーケーブルの悪影響が強いのか、比較検討できますね。
|
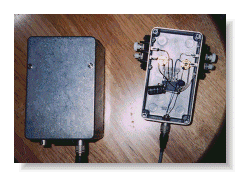
|
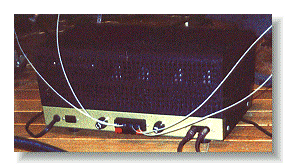
|
さて、ここで鈴木さん持参のクリスキット登場! 写真ではパワーしか写ってませんが、プリも持参してくださいました。クリスキットといえば、オーディオをかじった人なら名前を一度くらいきいたことがあるでしょう。そしてこの名前をきいたことがある人なら、これらのアンプの製造・販売をやってるクリス・コーポレーション社長にして設計者でもある桝谷氏のエキセントリックな経営方針についてもご存知でしょう。 でもどんな音が出てるのか、実際に聴いたことがある人はあまりいないかも。 |
|
で、聴いてみました。フツーです。一部の人からいわれているほどひどい音でもないし、一部の人が絶賛するほどすごい音でもない。ソフトでどこか懐かしい感じのする音です。これまた、細かいこといわなければこれでいいよねぇ、という音です。音について、あれこれ思い悩んで神経症気味になっちゃうくらいなら、クリスキットで音楽を楽しんだ方が健全だ、という発想は十分アリだとおもいます。値段もひどくボッているわけでもないし。 ちなみにプリのお顔とか、いろいろな細かいスペックやら、ラインナップやらといったクリスキット全般については、こちらをご覧ください。 |
|
さて「手作りアンプの会」から田中さんの紹介で田村さんがいらしてくださいました。「手作りアンプの会」といえば「超三極管接続」の真空管アンプ研究で有名なところです。でも有名だけどその音を聞いたことがある人は少ないかもしれません。その超三極管アンプを出品していただきました! まってましたぁ! 私、これを聴くために来たようなものというと、他の方に失礼かな。 写真のアンプの解説は、田村さんのメールを引用します。
|
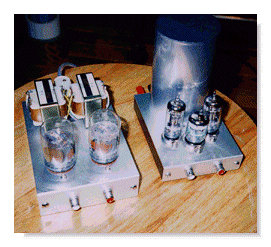
|
|
アルミみたいな円筒のトランスカバーのある方が6AN5を使った超3結合のアンプです。出力は0.3から0.5Wと言った所だと思います。ずんぐりした球2つの方は6AS11を使った強NF回路と呼んでいる回路を使用したアンプです。出力は0.3から0.5Wでしょう。共に、省電力アンプの実験(QRPアンプ)として作りました。1W以下でどこまで実用になるかを試す為のものです。
それぞれのアンプに関する解説は、それぞれリンク。6AN5と6AS11。 さて、音の感想。なんか変です。これまでのどんなアンプにもなかった鳴り方です。Hi-Fiとしての基本水準を十分に満たしているのですが、音の出方が違うのです。私は位相がなんか違うように思いました。人によっては低域と高域が強調されているように聞こえたようです。音場型ではなく音像型。音像ぎっしりで前に出るタイプの鳴り方で、ジャズライブの鳴り方なんかはよく再現できると思います。 たしかに目の前で楽器を鳴らされるとこういう風に聞こえます。でも、これまでのオーディオで音場を認識してきた私には、なにか変に聞こえるのです。これは不思議なアンプです。たしかに。
|

