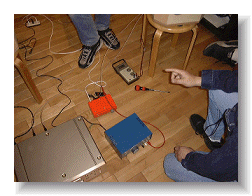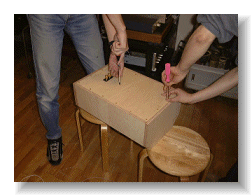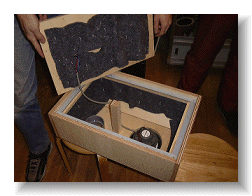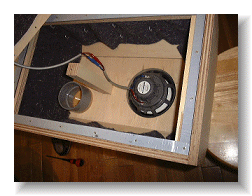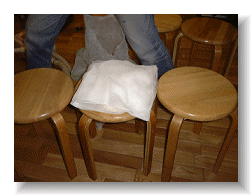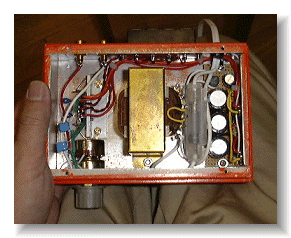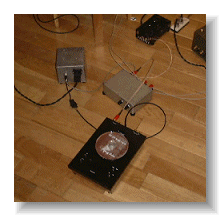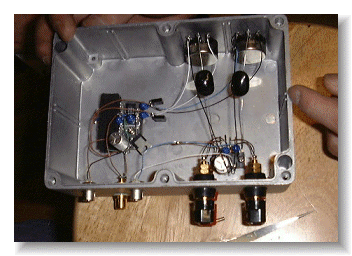スピーカーいじりいじり大会

|
4月8日の例会の報告。私(しらた)自身はシンポジウム出席と重なって欠席です。他の方からのメールの内容を総合する形で報告しますが、いつものようにいくかどうか。 さて、3月11日の例会の終わりころ、コイズミ無線の社長と「島田先生」なるオーディオ評論家の方が「スピーカー作ったんだけどいじってみる?」とFardayミーティング会場にお出ましになられました。そのスピーカーがこれ。条件は「外観に手を加えなければ何をしてもよい」ということでしたので、この島田先生のスピーカをオカズにいろいろと実験してみよう、というのが4月例会の課題となりました。このころパンヤ綿という綿を吸音財に使う実験が始まっていたので、ちょうどよく実験台がきたわけです。 さて、スピーカーについて。以下、他の方のメールの内容を引用しますが、誰の発言とは明示しませんのでご容赦ください。
|