
白田の情報法研究報告

 はじめに
はじめに

|
何をしているのか、よくわからないといわれたりする私の研究について、広く皆さんに知って頂くために、研究している内容をリアルタイムに提供することを目的としてここを開設しました。でも、最近は単なる近況報告みたいに... 相変わらずコピーライトの史的展開の方の直接販売受け付けてますので、よろしく(^^)/。 講義要項、講義資料、履修登録等など、講義に関することについては、下の小さなバナーをクリックしてください。

|
|
さあ、文月。本日は湿気ムンムンで辛かったです。さすがの私もネクタイなしで講義してしまいました。 さて、現代社会と法律学とエレクトロニクスメディア論は、PCによるプレゼンテーションで講義をしているのですが、そろそろ内容をより高度で見やすいものに作り変えたくなっています。ところが、私にはたいした研究予算もなく、バイトを雇うお金などとてもありません。しかし、私一人で改定作業をすれば、またまた夏休みがルーティン作業でつぶれてしまいます。どうしたものか...。とノイローゼになりそうなほど悩んだ挙句、次のことに興味がある人を募集。 ... 募集したら応募がありました。ありがとうございます。
|
変革の世紀去年の春に、NHKのディレクター井出さんの訪問を受けました。「変革の世紀」という番組で知的財産権について取り上げたいというので相談にいらしたのです。私は私のずいぶん昔の研究の記憶をたどりながら、現在の著作権制度が本来の目的から逸脱しつつある、ということについて説明しました。非常に込み入った複雑な経緯ですので、私はうまく説明できませんでした。それでとにかく井出さんに「コピーライトの史的展開」を読んでくださるようお願いしました。
|

|
|
それがようやく2002年7月14日に放送されました。エンディングに私の名前が出ているのを見て、何だか嬉しくなったのでキャプチャ画像を掲げます。著作権のなにかの権利に引っかかってるということでNHKから警告がこないことを祈りつつ...
|
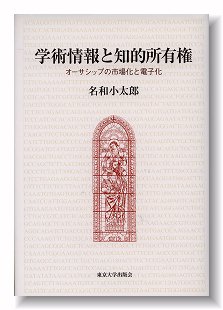
|

|
ちょうど折りよく、知的財産権のヤミクモな拡大に警鐘を鳴らすような本が出版されています。いずれも「コピーライトの史的展開」を引用してくださってます。名和先生の「学術情報と知的所有権」も、山田先生の「日本文化の模倣と創造」も、私に時間があったら私自身で取り組みたいと思っていたテーマでした。 とくに山田先生の著書については、まさに我が意を得たりの感じをもちます。とくに後半において、ハッカー文化と日本の文化との関連について述べられていたりして、私のHPをちょくちょく見にくるようなハッカータイプの人にも強くお勧めできます。というかぜひ読んでほしい。 大学の先生になってしまって、学術振興会時代のように思うままに研究できるという状態ではなくなった私にとっては、嬉しいような悔しいような感じがするこの二冊。これも知の連鎖、知の連歌だと思い、また誰かがさらにこの分野の研究を広げていくことを期待することにしましょう。
|
| [過去のトップページ] >> 97年8月 / 97年12月 / 98年1月 / 98年4月 / 98年5月 / 98年12月 / 99年4月 / 99年12月 / 00年2月 / 00年3月 / 00年6月 / 00年7月 / 00年8月 / 00年10月 / 00年12月 / 01年1月 / 01年2月 / 01年3月 / 01年5月 / 01年8月 / 01年11月 / 02年1月 / 02年3月 / 02年4月 / 02年7月 | |

 注意
注意

|
ここに掲載されている文書の内容は「無保証」 です。従って、ここに掲載されている文書は「見本」であると御理解ください。また、御意見・御批判は歓迎しますが、それらは必ず「完全版」について行って下さい。完全版はポストスクリプトファイル 、DVIファイル、またはPDFファイルで提供します。ポストスクリプトやDVIファイルが必要な方は私にお手紙ください。個別にファイルをさし上げます。 エキスパンドブックやPDF等の電子テキスト一般の読み方についての解説については、 こちらをご覧ください。 latex2htmlがうまく使えなかったので、自前のコンバータを作って LaTeXの原稿からHTMLファイルを作成しています。このため、LaTeXで使用される記述法を完全にHTMLに置き代えられていないので、時々、意味不明の記号が残っていたりします。
|

 履歴書 履歴書
| |
 小論集 小論集
| |
 ネット・ベンチャーにおける法的コスト, 一橋論叢, 128巻4号, 2002年10月 ネット・ベンチャーにおける法的コスト, 一橋論叢, 128巻4号, 2002年10月
| |
 情報時代における言論・表現の自由, 青空文庫, 2002年10月13日 情報時代における言論・表現の自由, 青空文庫, 2002年10月13日
毎年思うのですが、毎年、毎年同じことを話すのって苦痛ですよね。学生さんたちは初めて聴く話でしょうけど、こっちは基本的に同じ話を繰り返しているのです。で、恐ろしいことに以前やっていたことをだんだん忘れていくんですよ。私の記憶力って「トコロテン」みたいなもんなんですな。で、講義の基本的な部分は、こうして文章にしていって講義の時に「読め!」とか言って済ませてしまって、先の議論に進みたいと思ってたりします。 |  |
 著作権関連 8項目, 北川 高嗣 他編, 情報学事典, 弘文堂, 2002年6月 著作権関連 8項目, 北川 高嗣 他編, 情報学事典, 弘文堂, 2002年6月
| |
 文化不況, 某総合研究所にて2001年10月頃発表, 2002年3月26日公開 文化不況, 某総合研究所にて2001年10月頃発表, 2002年3月26日公開
| |
 サイバー空間の世界観, 朝日新聞夕刊 「ねっとアゴラ」, 2002年3月22日 サイバー空間の世界観, 朝日新聞夕刊 「ねっとアゴラ」, 2002年3月22日
| |
 判決文翻訳 Sony Computer Entertainment America. Inc. v. Connectix Corp., 2000 U.S.App. LEXIS 1744., 2002年2月 判決文翻訳 Sony Computer Entertainment America. Inc. v. Connectix Corp., 2000 U.S.App. LEXIS 1744., 2002年2月
| |
 「包括メディア産業法」への私案, in 21世紀型情報化社会への展望, 国際大学Glocom, 2002年3月 「包括メディア産業法」への私案, in 21世紀型情報化社会への展望, 国際大学Glocom, 2002年3月
|  |
 私家版・プロバイダ責任法についての解説と考察, オンライン・コミュニティへのお年玉, 2002年1月 私家版・プロバイダ責任法についての解説と考察, オンライン・コミュニティへのお年玉, 2002年1月
|  |
 山根 信二、辰己 丈夫、白田 秀彰 保険におけるセキュリティ格付け機関についての検討, 2001年10月 コンピュータ セキュリティ シンポジウム にて報告 (報告者 山根 信二) 山根 信二、辰己 丈夫、白田 秀彰 保険におけるセキュリティ格付け機関についての検討, 2001年10月 コンピュータ セキュリティ シンポジウム にて報告 (報告者 山根 信二)
|
 |
 グリゴリの捕縛 あるいは 情報時代の憲法について, 青空文庫, 2001年9月 Expand book版 2001年11月 グリゴリの捕縛 あるいは 情報時代の憲法について, 青空文庫, 2001年9月 Expand book版 2001年11月
富田さんにお願いして、こんなに立派な  にしていただきました。 にしていただきました。[注意!] この Expandbook ファイルは、Macintosh 用 BookBrowser 1.6.9.88 で、システムフォントが表示されなくなるという問題を発生させる可能性があることが報告されています。Machintosh でご覧の方は、BookBrowser 1.7以降でご覧ください。Windows 用の BookBrowserでは問題は生じません。 井上さんとの間の「グリゴリの捕縛」に関する公開往復書簡もご覧ください。 |
 |
 辰己 丈夫、山根 信二、白田 秀彰 ネットビジネス業者の「プライバシー保護対策」評価の提案, 2001年3月 情報処理学会 第62回全国大会にて報告 (報告者 山根 信二) 辰己 丈夫、山根 信二、白田 秀彰 ネットビジネス業者の「プライバシー保護対策」評価の提案, 2001年3月 情報処理学会 第62回全国大会にて報告 (報告者 山根 信二)
|
 |
 告知 告知
| |
 告知 告知
| |
 レイアウト・フォーマット --- 知恵蔵事件, in 別冊ジュリスト 著作権判例百選, 有斐閣, 2001年4月 レイアウト・フォーマット --- 知恵蔵事件, in 別冊ジュリスト 著作権判例百選, 有斐閣, 2001年4月
| |
 The Origin of Two American Copyright Theories: A Case of the Reception of English Law, The Journal of Arts Management, Law and Society, Vol. 30, No. 3, (Fall 2000, Heldref Publications) The Origin of Two American Copyright Theories: A Case of the Reception of English Law, The Journal of Arts Management, Law and Society, Vol. 30, No. 3, (Fall 2000, Heldref Publications)
| |
 デジタル/ネットワーク時代・著作権の臨界 (改題), 2000年11月30日 国際大学グローコム デジタル著作権研究会 第一回オープン・フォーラムにて報告 デジタル/ネットワーク時代・著作権の臨界 (改題), 2000年11月30日 国際大学グローコム デジタル著作権研究会 第一回オープン・フォーラムにて報告
これまた、詳細な文献リストや脚注をつける作業ができないので、公開できません。大学をしばらく休んで自分の書いたものの整理をしたいです。 | |
 情報法の背景, 2000年5月12日 一橋大学 法文化構造論にて報告 情報法の背景, 2000年5月12日 一橋大学 法文化構造論にて報告
| |
 著作権の情報流通技術決定論 仮説, 2000年3月18日 国際日本文化研究センターにて報告 著作権の情報流通技術決定論 仮説, 2000年3月18日 国際日本文化研究センターにて報告
[愚痴] どうも、この論文はお蔵入りになりそうです。一つ一つ、文献の該当個所を挙げるような地道な作業に費やす時間が取れないため、内容的には問題なくても公開できないのか悩みです。 ↑と書きましたが、せっかくやった仕事ですし、学生さんの何らかの参考になるかと思いまして、「脚注ほとんどなし」状態で公開することにしました。もちろん、まともな論文ではありませんから、学術論文への引用はお避け下さい。 むしろ大学院あたりの学生さんが、この論文の内容を引き継いで検証してくれることを希望します。(2002年3月14日)
| |
 倫理問題, in bit別冊「情報セキュリティ」, 共立出版, 2000年1月 倫理問題, in bit別冊「情報セキュリティ」, 共立出版, 2000年1月
この「倫理問題」の原稿は、下の「コンピュータ・ネットワークにおける自由と倫理」で用いた論文に加筆したものです。重要な部分について加筆したので、ご批判は書籍に掲載されたものに対して行ってください。明大情報科学センター紀要には、私の口述内容が掲載されておりまして、論文は掲載されませんでした。 | |
 もう一つのプライバシーの話 --- 中学生、高校生のためのプライバシー問題へのヒント ---, 青空文庫, 1999年9月 もう一つのプライバシーの話 --- 中学生、高校生のためのプライバシー問題へのヒント ---, 青空文庫, 1999年9月 |  |
 求人・求職活動における個人情報保護に関する報告, in インターネット求人・求職情報の現状とその課題, 社団法人 全国求人情報誌協会, 1999年3月 求人・求職活動における個人情報保護に関する報告, in インターネット求人・求職情報の現状とその課題, 社団法人 全国求人情報誌協会, 1999年3月
|
 |
 誰をどのように護るのか --- CDAの目的と効果について, 1999年1月30日, 情報処理学会 電子化知的財産社会基盤研究会にて報告. 情処研報, Vol.99, No.11. 誰をどのように護るのか --- CDAの目的と効果について, 1999年1月30日, 情報処理学会 電子化知的財産社会基盤研究会にて報告. 情処研報, Vol.99, No.11.
|
 |
 コンピュータ・ネットワークにおける自由と倫理, 1998年11月21日, 明治大学情報科学センター情報教育研究会にて報告. コンピュータ・ネットワークにおける自由と倫理, 1998年11月21日, 明治大学情報科学センター情報教育研究会にて報告. | |
 判例解説 Cubby, Inc. v. CompuServe Inc., 776 F.Supp. 135 (1991), 「アメリカ法」 1998-1, 1998年7月31日 判例解説 Cubby, Inc. v. CompuServe Inc., 776 F.Supp. 135 (1991), 「アメリカ法」 1998-1, 1998年7月31日
|
 |
 もう一つの著作権の話 --- 中学生、高校生のための著作権の基礎理論 ---, 青空文庫,1998年7月 もう一つの著作権の話 --- 中学生、高校生のための著作権の基礎理論 ---, 青空文庫,1998年7月
ボイジャーの野口さんのおかげで、こんなに立派な  になりました。 になりました。 |  |
 コピーライトの史的展開 [知的財産研究叢書2],信山社,1998年7月 コピーライトの史的展開 [知的財産研究叢書2],信山社,1998年7月
|
 |
 アメリカ著作権理論の起源 -- アメリカにおけるイギリス法継受の一事例 --, 報告用 手許資料, 比較法研究 No. 60 (1999) 128. 1998年6月6日 比較法学会第61回総会 英米法部会. アメリカ著作権理論の起源 -- アメリカにおけるイギリス法継受の一事例 --, 報告用 手許資料, 比較法研究 No. 60 (1999) 128. 1998年6月6日 比較法学会第61回総会 英米法部会.
|
 |
 求人・求職活動における個人情報保護に関する報告, in インターネット求人・求職情報の現状とその課題 (中間報告書), 社団法人 全国求人情報誌協会, 1998年3月 求人・求職活動における個人情報保護に関する報告, in インターネット求人・求職情報の現状とその課題 (中間報告書), 社団法人 全国求人情報誌協会, 1998年3月
|
 |
 著作権の原理と現代著作権理論, 1998年1月31日 比較法史学会関東部会、2月2日 国際大学Glocom にて報告 著作権の原理と現代著作権理論, 1998年1月31日 比較法史学会関東部会、2月2日 国際大学Glocom にて報告
| |
 英米法系コピーライトに関する歴史的研究, 1997年5月 英米法系コピーライトに関する歴史的研究, 1997年5月
|
要旨 |
 情報テクノロジーの進展と法的課題 in 堀部政男・編著, 情報公開・プライバシーの比較法, 日本評論社, 1996年12月 情報テクノロジーの進展と法的課題 in 堀部政男・編著, 情報公開・プライバシーの比較法, 日本評論社, 1996年12月
| |
 アメリカにおけるインターネットへの司法権力の介入: IAJ News, Internet Association of Japan, Vol.3 No.1, 1996年4月 アメリカにおけるインターネットへの司法権力の介入: IAJ News, Internet Association of Japan, Vol.3 No.1, 1996年4月
|
 |
 比喩・概念・法 ---仮想空間を切り分けるもの(1)---: Smart Community, Smart Community 研究会, 1995年11月 比喩・概念・法 ---仮想空間を切り分けるもの(1)---: Smart Community, Smart Community 研究会, 1995年11月
| |
 アスペン・サミット オンライン ---ネットワーク時代の政府と共同体の役割---: Smart Community, Smart Community 研究会, 1995年10月 アスペン・サミット オンライン ---ネットワーク時代の政府と共同体の役割---: Smart Community, Smart Community 研究会, 1995年10月
| |
 ハッカー倫理と情報公開・プライバシー:「高度情報化の法体系と社会制度」 科学研究費補助金・重点領域研究報告書, 1995年3月 ハッカー倫理と情報公開・プライバシー:「高度情報化の法体系と社会制度」 科学研究費補助金・重点領域研究報告書, 1995年3月
|
 |
 ネットワーク上の名誉毀損と管理者の責任: レポート, 1994年4月 ネットワーク上の名誉毀損と管理者の責任: レポート, 1994年4月
[注意!!]このレポートで言及している「ニフティサーブ名誉毀損事件」に関する最初の判決が出たために、にわかにこのレポートへの関心が復活しているようですが、次の点にご注意。 | |
 コピーライトの史的展開 コピーライトの史的展開
|
 |
 法令用語と判例における「情報」: 「情報の瑕疵がもたらす民事上の責任に関する調査研究」 財団法人 比較法研究センター, 1993年6月 法令用語と判例における「情報」: 「情報の瑕疵がもたらす民事上の責任に関する調査研究」 財団法人 比較法研究センター, 1993年6月
|

 個人的キャンペーン
個人的キャンペーン

個人的キャンペーンがあまりに多くなってしまった(^^;;ので別ページに移動しました。

 リンク
リンク

 昔のWebサイトの内容を取り戻したい時に便利! 1997-8年くらいまで溯れます。 昔のWebサイトの内容を取り戻したい時に便利! 1997-8年くらいまで溯れます。
  日本の情報法関連のリソースが最も豊富に集められているサイトといえば、明治大学の夏井高人先生のページが代表的なものでしょう。継続的な更新作業に頭が下がります。 日本の情報法関連のリソースが最も豊富に集められているサイトといえば、明治大学の夏井高人先生のページが代表的なものでしょう。継続的な更新作業に頭が下がります。

|

|
タイトルページを短くするために、「付録」を別ページに移動しました。参考資料や、私の雑文、秀丸のマクロなどがあります。
|

|
|
白田 秀彰 (Shirata Hideaki) 法政大学 社会学部 助教授 (Assistant Professor of Hosei Univ. Faculty of Social Sciences) 法政大学 多摩キャンパス 社会学部棟 917号室 (内線 2450) e-mail: shirata1992@mercury.ne.jp |
